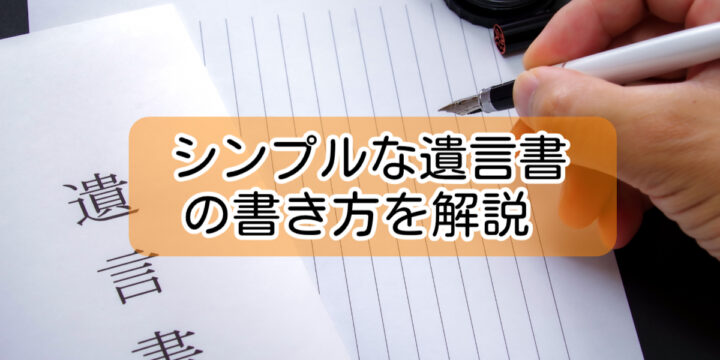相続が発生し、故人(被相続人)が所有していた不動産(土地や建物)の名義を相続人に変更する「相続登記」を進めようとした際、多くの方が直面する問題があります。
それは、「被相続人の最後の住所(住民票上の住所)と、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている住所が異なっている」というケースです。
登記簿には、被相続人がその不動産を取得した何十年も前の住所が記載されたまま、ということも珍しくありません。
「このままだと相続登記ができないのでは?」 「先に住所変更の登記が必要なの?」 「余計な費用や手間がかかるのでは?」
このような不安を感じる方も多いでしょう。
この記事では、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が異なる場合の相続登記について、必要な書類や具体的な手続きの流れ、そして注意点を、相続登記の専門家である司法書士の視点で徹底的に解説します。
なぜ登記簿上の住所と最後の住所が違ってしまうのか?
不動産の登記簿(登記事項証明書)には、その不動産の所有者の「住所」と「氏名」が記録されています。この住所は、その不動産を取得した時点(売買、相続、贈与などで名義人になった時)の住所が記載されます。
例えば、昭和50年にA市B町1番地1でマイホームを購入した場合、登記簿にはその住所が記載されます。その後、平成10年にC市D町2番地2へ引越し、そのまま令和7年に亡くなられた場合、以下のようになります。
- 登記簿上の住所: 昭和50年時点の「A市B町1番地1」
- 被相続人の最後の住所: 令和7年死亡時点の「C市D町2番地2」
本来、引越し(住所移転)をした場合、法務局で「登記名義人住所変更登記」を行い、登記簿上の住所を現住所に更新すべきです。しかし、この住所変更登記は、2026年(令和8年)4月までは義務化されておらず(※)、また、登記をしても特にメリットを感じにくいため、何十年も放置されているケースが非常に多いのです。
(※ 2026年4月からは、不動産所有者の住所変更登記が義務化され、正当な理由なく2年以内に登記しないと過料の対象となります)
登記簿上の住所と最後の住所が違うとなぜ問題なのか
相続登記を申請する際、法務局は「登記簿に記載されている所有者」と「亡くなった被相続人」が間違いなく同一人物であることを確認する必要があります。
しかし、住所が異なっていると、法務局は「登記簿上のA市B町1番地1のAさん」と「亡くなったC市D町2番地2のAさん」が、同姓同名の別人である可能性を排除できません。
そのため、相続登記の申請において、「登記簿上の人物」と「亡くなった被相続人」が同一人物であることを公的な書類で証明する必要が生じるのです。
住所変更登記は省略できる
かつては、この問題を解決するために、相続登記の前提として、亡くなった被相続人の「登記名義人住所変更登記」を申請し、登記簿上の住所を最後の住所に直してから、相続登記を行うのが一般的でした。
しかし、この方法では「住所変更登記の登録免許税(不動産1個につき1,000円)」や司法書士報酬が別途かかり、相続人の負担となっていました。
そこで、平成29年(2017年)3月22日以降の登記実務の取り扱い変更により、相続登記の場合に限り、一定の書類を添付すれば、この住所変更登記を省略して、直接「相続登記」ができるようになりました。
住所変更登記を省略するための条件
省略を可能にするためには、以下の2点を満たす必要があります。
- 登記簿上の住所(旧住所)から最後の住所(新住所)までの「住所の変遷(つながり)」を証明する公的な書類を添付すること。
この「住所のつながりを証明する書類」こそが、今回の手続きにおける最大の鍵となります。
必要な書類:通常の相続登記 +「住所のつながりを証明する書類」
このケースの相続登記では、通常の相続登記で必要な書類に加えて、前述の「住所のつながりを証明する書類」が必要になります。
通常の相続登記に必要な書類(共通)
まずは、どのような相続登記でも共通して必要となる基本的な書類です。
【被相続人(亡くなった方)に関する書類】
- 出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍): 相続人が誰であるかを確定するために必要です。
- 住民票の除票(または戸籍の附票): 最後の住所地を証明します。(これが「住所のつながり」の証明も兼ねる場合があります)
【相続人(財産を取得する方)に関する書類】
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 遺産分割協議書: 法定相続分と異なる割合で相続する場合や、特定の相続人が単独で取得する場合に必要。相続人全員の実印を押印します。
- 相続人全員の印鑑証明書: 遺産分割協議書に押印した実印の証明です。期限はとくにありません。
- 固定資産評価証明書(最新年度のもの): 登録免許税(登記の税金)を計算するために必要です。
※遺言書がある場合は、遺言書(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認済証明書)が必要となり、一部の書類が不要になる場合があります。
【最重要】住所のつながりを証する書類について
ここからが、最も重要ですが、登記簿上の住所(旧住所)と最後の住所をつなげるためには、以下の書類を準備する必要があります。
・戸籍の附票
戸籍の附票とは、その本籍地にある間の、「住所履歴」が一覧となって記録された書類です。戸籍とセットで役所にて管理されています。
戸籍の附票は、被相続人の「最後の本籍地」の役所(市区町村役場)で取得します。
この戸籍の附票に、登記簿上の住所(旧住所)と、最後の住所の両方が記載されていれば、それだけで「住所のつながり」を証明することができます。
・住民票の除票
住民票の除票とは、本人の死亡や転籍により、その市区町村の住民基本台帳から除かれた住民票のことです。
被相続人の住民票の除票は、被相続人の「最後の住所地」の役所で取得します。
住民票の除票には、通常は「一つ前の住所」が記載されています。そのため、登記簿上の住所が一つ前の住所であれば、これだけでも証明ができます。稀に二つ前の住所まで記載されていることもあります。
パターン別の住所のつながりを証する書類
住所のつながりを証明しようと思うと、実際にはなかなかスムーズにいかないケースも多いです。
パターン1:戸籍の附票(または住民票の除票)1枚でつながる場合
これが最も簡単なケースで、これ1枚で全ての住所のつながりを証明することができます。
- (例)最後の本籍地で「戸籍の附票」を取得したら、登記簿上の住所「A市B町1-1」から、最後の住所「C市D町2-2」までの変遷がすべて記載されていた。
この場合は、その戸籍の附票または住民票の除票を添付すればOKです。
バターン2:戸籍の附票が複数必要な場合(転籍や婚姻など)
被相続人が結婚や転籍(本籍地を移すこと)をしていると、戸籍の附票はその時点(転籍時)で新しく作り直されます。
以下のような例の場合です。
- 登記簿上の住所「A市B町1-1」に住んでいた時(当時の本籍地:X市)
- その後、転籍して本籍地をY市に移した。
- 最後の住所「C市D町2-2」に住んでいた時(本籍地:Y市)
この場合、最後の本籍地(Y市)で「戸籍の附票」を取得しても、記載されているのはY市に本籍を置いてからの住所履歴(C市D町2-2など)だけです。登記簿上の住所(A市B町1-1)は記載されていません。
対処法としては、以下のような方法があります。
- 転籍前の本籍地(X市)の役所に対しても、**「戸籍の附票の除票(除附票)」**を請求します。
- Y市の「戸籍の附票」と、X市の「戸籍の附票の除票」の2通(あるいはそれ以上)を組み合わせることで、A市B町1-1 → ... → C市D町2-2 という住所の変遷を証明します。
パターン3:書類がすでに廃棄されていて、つながらない場合
最大の難関がこのケースです。
住民票の除票や戸籍の附票の除票は、以前は保存期間が「5年間」と定められていました(現在は法改正で150年)。そのため、古い住所履歴は役所で**「保存期間経過のため廃棄済み」**となっていることが多々あります。
対処方法としては以下のような方法があります。
- 「廃棄証明書(不存在証明書)」の取得:まず、役所から「戸籍の附票の除票は廃棄した」という旨の証明書(発行手数料がかかる場合とかからない場合があります)を取得します。
- 代替書類の準備:公的な書類で住所の変遷が追えない以上、他の書類で「登記簿上の人物=被相続人」であることを証明(疎明)します。
- 登記済権利証(いわゆる「権利証」)の原本:被相続人が不動産を取得した際に発行された「登記済」のハンコが押された書類、または「登記識別情報通知」です。これは被相続人本人しか持っていないはずの書類であり、非常に強力な証明となります。法務局に原本を提示します。(コピー不可。原本は確認後返却されます)
- 上申書:「登記簿上の人物(A市B町1-1のA)と、被相続人(C市D町2-2のA)は、間違いなく同一人物です」という内容の書面を作成します。そこに相続人全員が署名し、実印を押印します。あわせて、相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に添付するものと兼用可)を添付します。
- その他の補強書類(あれば尚良い):被相続人宛の「固定資産税の納税通知書」(登記簿上の不動産の納税義務者として記載されているため)。登記簿上の住所が記載されている古い公共料金の領収書や手紙など(証明力は弱いですが、無いよりは良いです)
法務局への事前相談
廃棄済みで戸籍の附票が取れず、権利証も見当たらない場合は、上申書だけで受理してもらえるか、必ず事前に管轄の法務局に相談してください。法務局の登記官の判断によって、追加の書類(例: 相続人以外の第三者による証明書など)を求められる可能性もゼロではありません。住所のつながりを証する書類については、各法務局により判断が異なることがありますので、心配な場合は、必ず事前に法務局に確認を取っておくといいでしょう。
相続登記の義務化と専門家への相談
相続登記は「義務」です
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記は義務化されました。 「相続(または遺言)により不動産を取得したことを知った日から3年以内」に登記を申請しなければなりません。
過去の相続(令和6年4月1日より前に発生した相続)も対象となり、3年間の猶予期間(令和9年3月31日まで)が設けられています。
正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
「住所が違って面倒だ」と放置しておくと、将来的にペナルティを受けるリスクがあります。
手続きが困難な場合は司法書士へ
ここまで解説した通り、「住所のつながり」の証明は、相続登記の中でも特に手間のかかる手続きの一つです。
- 複数の役所に戸籍の附票を請求する必要がある(郵送でのやり取りに時間がかかる)
- 古い戸籍(手書き)の解読が難しい
- 書類が廃棄されていて、上申書の作成や法務局との調整が必要
- 権利証が見つからない
- 相続人が多い、または疎遠である
上記のようなケースでは、ご自身で手続きを進めるのは非常に困難です。
相続登記の専門家である司法書士に依頼すれば、戸籍謄本や戸籍の附票の収集、遺産分割協議書の作成、法務局との調整、そして登記申請まで、すべてを代理で行うことができます。
費用はかかりますが、複雑な手続きにかかる時間、労力、そして精神的なストレスを大幅に軽減できるメリットは非常に大きいと言えます。
まとめ
被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が違っていても、慌てる必要はありません。
「住所のつながりを証明する書類(戸籍の附票など)」を揃えることで、住所変更登記を省略して、相続登記を申請することが可能です。
まずは、被相続人の最後の本籍地で「戸籍の附票」を取得し、登記簿上の住所が記載されているかを確認することから始めましょう。
もし書類が廃棄されていたり、手続きが複雑でご自身での対応が難しいと感じたりした場合は、相続登記が義務化された今、放置せずに、お近くの司法書士に相談することをおすすめします。
相続に関連する記事
シンプルな遺言書の書き方
2025年12月29日
法定相続情報一覧図の取得方法や必要書類について司法書士が解説
2025年9月11日
遺留分を事前に放棄してもらうことはできる?
2025年8月24日
遺留分とは、兄弟姉妹を除く一定の相続人(配偶者・子・直...