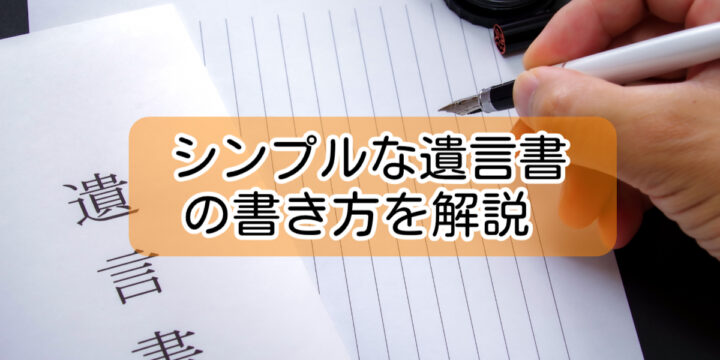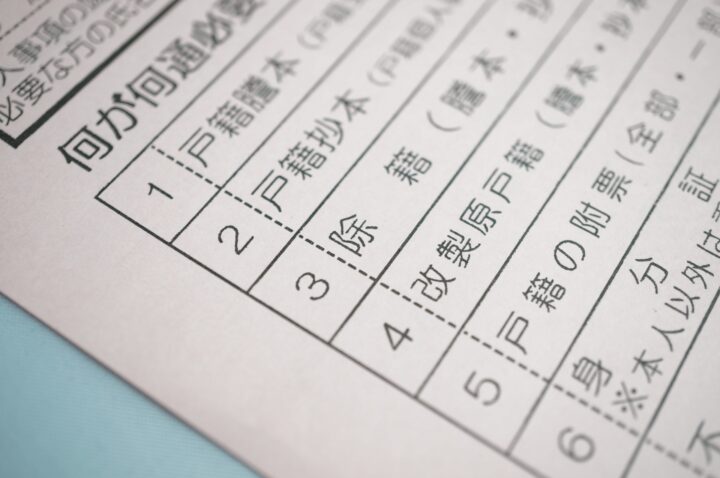相続対策を検討している方からよくいただくご相談のひとつに、「相続人に遺留分を事前に放棄してもらうことはできないか?」というものがあります。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く一定の相続人(配偶者・子・直系尊属)に、最低限保証される相続財産の取り分を認めた制度です。遺言で全ての財産を特定の人に遺贈しても、他の相続人は遺留分侵害額請求を通じて取り戻すことが可能です。
しかし、事前に相続人から「遺留分を放棄します」と言ってもらえれば、将来の紛争を避け、自由度の高い相続設計ができるのではないか、そう考える方も少なくありません。本記事では、相続の専門家の視点から、遺留分の事前放棄が可能かどうか、その方法や注意点を詳しく解説していきます。

相続人に保証された必要最低限の生活保障遺留分とは
遺留分の基本知識
遺留分とは、被相続人の意思を尊重しつつも、残された家族の生活保障を図るために設けられた制度です。遺留分を有するのは以下の相続人です。
- 配偶者
- 子(または代襲相続する孫)
- 直系尊属(父母・祖父母など)
ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。ここが重要なポイントです。
遺留分の割合
遺留分の割合は、法定相続分の 1/2(直系尊属のみが相続人の場合は1/3) とされています。
例えば、子が2人いて遺産が1億円の場合、法定相続分はそれぞれ1/2です。その1/2のさらに1/2、つまり各人2,500万円が遺留分となります。つまり、子はそれぞれ2,500万円までは取り分が保証されるということです。
遺留分は放棄できる?
遺留分の事前放棄は可能です。ただし、口頭の約束や単なる合意書では効力がなく、家庭裁判所の許可を得なければなりません。民法第1049条には、相続開始前における遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を得てすることができると規定されています。つまり、相続人が「私は遺留分を請求しません」と宣言しても、それだけでは無効であり、裁判所の判断があって初めて法的効力が生じるのです。
家庭裁判所の許可が必要な理由
相続人を保護するという観点
遺留分は生活保障の性格を持つため、安易に放棄してしまうと将来の生活に支障が出る恐れがあります。特に被相続人と相続人との力関係によって、不当に放棄を迫られるリスクもあります。
そのため、家庭裁判所は以下のような点を審査します。
- 遺留分の放棄が自分の意思によるものか
- 放棄をする相続人にとって不利益が大きすぎないか
- 被相続人から放棄の見返り(贈与や養育など)があるか
これらを確認し、正当な理由が認められる場合のみ、放棄が許可されます。つまり、簡単に放棄ができるかというと、そんなに簡単ではありません。
遺留分放棄の具体的な手続き
1.家庭裁判所への申立て
相続開始前に、放棄を希望する相続人本人が家庭裁判所に申立てを行います。申立て先は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
2.必要書類
- 遺留分放棄許可の申立書
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 放棄に至った経緯を説明する書面
- 郵便切手や収入印紙など手続きに必要な手数料
3.家庭裁判所の審理と判断
家庭裁判所は申立人から事情を聴取し、放棄が合理的かどうかを判断します。場合によっては、放棄を希望する理由を被相続人や他の相続人からも確認されることがあります。
4.許可の審判
裁判所が妥当と認めれば、遺留分の放棄が許可されます。この審判が確定すれば、放棄は有効に成立し、将来の相続時に遺留分を主張することはできなくなります。
遺留分の許可が認められるケースとは
家庭裁判所が許可する典型的な例としては、以下のような事情が挙げられます。
- 被相続人からすでに多額の贈与を受けており、他の相続人と公平を保つために放棄する場合
- 被相続人の事業承継のために特定の子に財産を集中させたい場合
- 放棄する代わりに、生前に一定の資金援助や不動産を受け取っている場合
逆に、「ただ親から頼まれたから」という理由だけでは許可が下りないことが多いです。
遺留分の放棄のメリットとデメリット
遺留分放棄のメリット
1.相続争いを未然に防止できる
後から遺留分侵害額の請求をされなくなるため、遺言内容を確実に実現できます。
2.事業承継をスムーズに進められる
家業の会社株式や事業用資産を後継者に集中して承継させられます。
3.遺産分割の自由度が増す
特定の相続人や第三者に財産を渡したい場合にも柔軟に対応可能です。
遺留分放棄のデメリット
1.家庭裁判所の審査が厳しい
安易に認められるわけではなく、時間と労力がかかります。
2.相続人の将来の生活保障が弱まる
一度放棄すると後から取り消せないため、相続人にとっては大きなリスクです。
3.家族間の感情的対立の火種になることもある
「放棄を強要された」と感じる相続人が出れば、かえってトラブルになる恐れがありますので、慎重な判断が必要です。
遺留分放棄と相続放棄の違い
しばしば混同されがちですが、遺留分の放棄と相続放棄は全く異なります。遺留分放棄は相続開始前に家庭裁判所の許可を得て行うもので、対象となるのは遺留分という権利に限られます。一方、相続放棄は相続開始後に行う手続きであり、相続そのものを放棄するため、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がなくなります。両者は似て非なるものですので、目的に応じて正しく使い分ける必要があります。
遺留分放棄を検討すべき場面
- 事業承継を予定しており、株式を後継者に集中させたい
- 不動産を特定の相続人に残したい
- すでに生前贈与で十分な資産を渡している
- 再婚家庭で、先妻の子とのトラブルを避けたい
これらの場合、遺留分放棄を活用することで、将来の紛争を大きく減らすことが可能です。
まとめ
遺留分は相続人の生活を守る大切な制度ですが、遺言の自由度を制約する側面もあります。そのため、法律は家庭裁判所の許可を条件に相続開始前の遺留分放棄を認めています。放棄を有効に行うためには、申立書の提出から審理、許可審判に至るまでの手続きをきちんと踏む必要があり、口約束や私的な契約書では意味を持ちません。
遺留分の事前放棄を検討する場合には、メリットとデメリットを正しく理解し、家庭裁判所が許可を出すかどうかを見極めながら進めることが重要です。特に事業承継や再婚家庭など、相続トラブルが生じやすい場面では有効に機能しますが、相続人に不利益が大きすぎる場合には認められない可能性もあります。
実際に遺留分放棄を進める際には、法律の専門家に相談し、家庭裁判所の審査に耐えうるだけの合理的な理由や証拠を整えることが求められます。相続対策を確実に進めたいと考えている方は、早めに弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
相続に関連する記事
シンプルな遺言書の書き方
2025年12月29日
被相続人の最後の住所が登記簿上の住所と違う場合の相続登記に必要な書類と手続きを徹底解説
2025年10月30日
それは、「被相続人の最後の住所(住民票...
法定相続情報一覧図の取得方法や必要書類について司法書士が解説
2025年9月11日