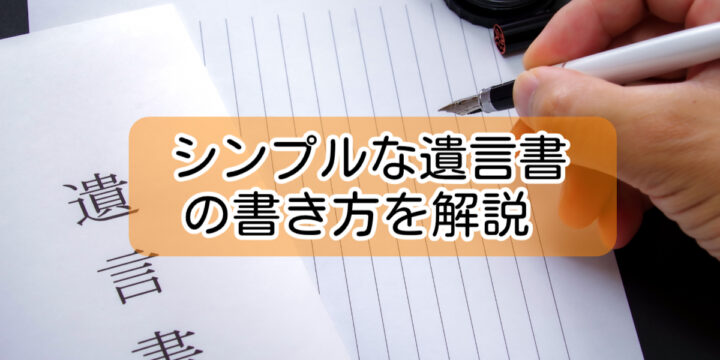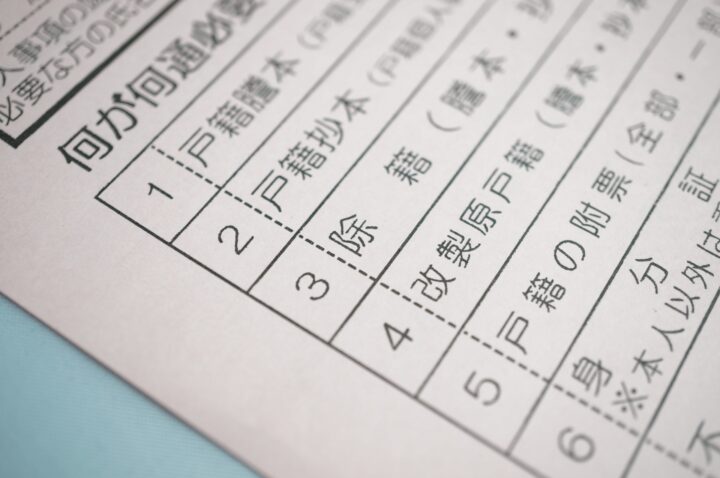相続税っていくらかかるものなの??
「親が亡くなったけど、相続税を払わないといけないんだよね?」
「親の遺産がそこそこあるんだけど、相続税の申告って必要なの?」
相続発生の前と後を問わず、このような相続税についての不安をお持ちの方も少なくありません。相続が発生したら相続税がかかるものだと思われている方も多くおられます。
特に50代以降のの方々は、親の介護やご自身の終活を視野に入れて、相続税について知っておきたいと思われます。
この記事では、相続税が発生する基準額や税率、そして節税のポイントなどを解説します。
相続税がかかるのはどんなとき?
相続税は基礎控除を超えた場合に発生する
相続税が課税されるかどうかは、相続する財産の合計が「基礎控除額」を超えるかどうかで決まります。
この基礎控除額は、次の計算式で求められます。
相続税の基礎控除額
(3,000万円+600万円)×法定相続人の数
(例)相続人が2人の場合の基礎控除額
3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
つまり、相続する財産の合計が4,200万円を超える場合に、超過分に対して相続税がかかるということになります。裏を返せば、4,200万円に満たなければ、相続税を払う必要はないということです。
課税される遺産とは?対象となる財産一覧
相続税の対象になるのは、次のような資産です。
・現金・預貯金
・不動産(土地・建物)
・株式や投資信託などの金融資産
・生命保険金(非課税枠を超える部分)
・自動車・貴金属・骨董品などの動産
さらに、相続発生前3年以内に贈与された財産(生前贈与)も、一部相続税の対象となるので注意が必要です。
相続税の税率は累進課税で高い相続税の税率と計算方法
相続税の税率は累進課税方式で、相続財産の金額が高くなるほど税率も上がっていきます。
| 課税対象金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| ~1,000万円 | 10% | 0円 |
| ~3,000万円 | 15% | 50万円 |
| ~5,000万円 | 20% | 200万円 |
| ~1億円 | 30% | 700万円 |
| ~2億円 | 40% | 1,700万円 |
| ~3億円 | 45% | 2,700万円 |
| ~6億円 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
※「各人の法定相続分で分けたと仮定した場合」の金額に応じて税率を決定し、最終的に実際の取得額に応じて配分していきます。
実際の相続税の流れと計算例
(例)遺産総額6,000万円で相続人2人(配偶者と子)の場合
・基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
・課税対象額:6,000万円-4,200万円=1,800万円
これを法定相続分(配偶者1/2、子1/2)で分けたと仮定すると、
1人あたり900万円が課税対象です。
→ 900万円の税率は10%、控除額0円
→ 税額:900万円 × 10% = 90万円
これが2人分で、相続税の合計は180万円となります。
※実際には配偶者控除などの特例により、配偶者は税額が0円になることもありますので注意が必要です。
相続税が実際に支払われる割合は?
国税庁のデータによれば、相続税が実際に課税される割合は全体の8〜10%程度です。つまり、90%以上の方は相続税を支払っていないということになります。
しかし都市部で不動産を所有している方、預金や株式の資産がある方は、意外と基礎控除を超えるケースも多いため、油断は禁物です。
相続税を軽減する特例方式
配偶者の税額軽減
配偶者が取得する財産については、次のいずれかまで相続税がかかりません。
・1億6,000万円まで
・法定相続分まで
配偶者の生活保障の観点から、大幅に優遇されている制度です。
小規模宅地等の特例
被相続人が居住していた土地や事業用地については、一定の要件を満たすと最大80%の評価減が認められます。
・居住用宅地:330㎡まで80%減額
・事業用宅地:400㎡まで80%減額
この特例によって、不動産評価額が数千万円単位で下がり、結果的に相続税がかからなくなることもあります。
相続税の申告と納付の期限
相続税の申告と納付は、相続開始(通常は被相続人の死亡日)から10か月以内に行う必要があります。
【注意点】
・土地や不動産の評価・分割協議に時間がかかるケースが多いため、早めの準備が重要
・延滞や無申告による加算税・延滞税が発生することもある
相続税対策のポイント
生前贈与の活用
・年間110万円までの贈与は非課税(暦年課税)。毎年少しずつ贈与することで少しずつ財産を移動させることができます。
・教育資金贈与や結婚・子育て資金の一括贈与も一定条件で非課税。
遺産の把握と、分割払いプランを早めに立てる
・不動産・預金・有価証券などの現状把握
・揉めやすい財産(不動産が1つだけ、など)は生前からの話し合いが重要
相続の専門家へ相談する
・適切な評価や申告、節税のアドバイスを得るためには専門家の力が不可欠です。できれば相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。特に土地を多く持っている場合は、専門家に相談することで、土地の評価を下げてもらうことができるかもしれません。
まとめ
相続税は、すべての方に発生するわけではありませんが、基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人)を超えると申告義務が生じます。
特に、
・都市部に土地や家を持っている
・預貯金がある程度まとまっている
・生前贈与をしていた
といったケースでは、想像以上に相続税が発生する可能性があります。
「うちは関係ない」と思わずに、一度、財産の棚卸しと相続人の確認をしておくことが、ご自身の将来の安心にもつながります。
イメージとしては、5,000万円くらいの財産がある場合は、相続税がかかる可能性もあることも視野に入れていいと思います。
弁護士、税理士、司法書士、FP相続の専門家に相談するメリット
相続は一度きりの大きな手続きです。遺産分割や税金の計算ミスが後のトラブルにつながることもあります。信頼できる弁護士や税理士、司法書士などに早めに相談し、適切な対策を講じることが、家族の幸せと安心につながる第一歩です。
司法書士ローワン綜合法務事務所では、相続専門の税理士とも連携しておりますので、相続税がいくらかかるのか不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
相続に関連する記事
シンプルな遺言書の書き方
2025年12月29日
被相続人の最後の住所が登記簿上の住所と違う場合の相続登記に必要な書類と手続きを徹底解説
2025年10月30日
それは、「被相続人の最後の住所(住民票...
法定相続情報一覧図の取得方法や必要書類について司法書士が解説
2025年9月11日